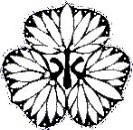市川三郷町立市川南小学校 いじめ防止基本方針
1 はじめに
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利及び基本的人権等を著しく侵害し、児童の 心身の健全な成長を阻害し、人格の形成等に甚大かつ重大な危険を生じさせるものである。
また、いじめは、いつでも、どこからでも、どの児童にでも起こり得るものであり、どの児童 も被害者と加害者の両方になり得るという危険性をもはらんでいる。こうした事実をふまえて、
「いじめは絶対に許さない」
「いじめは卑怯な行為である」
※子どもは、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚 し、いじめを許さない子ども社会の実現に努める。
「いじめは、どの子でもどの学校でも起こり得る最も身近で深刻な人権侵害案件である」
ことを念頭に、「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」、「いじめへの早急な対処措置」 について、市川南小学校としての共通理解を図り、組織的に対応していく。
特に、いじめの予防と早期発見に重点的に取り組んでいくと共に、いじめが発生してしまった 場合には、児童の尊厳を最大に重視し、教育委員会や地域、家庭、関係機関との連携のもと、早 急にいじめ根絶に向けて、組織をあげて適切な対処に全力で取り組むようにする。さらに、常に いじめがなく安心して生活することができる学校の実現と維持のために、いじめ防止に係る取り 組みを定期的にふり返り、改善を加えていくようにする。
2 いじめの定義と基本認識
(1)定義 「いじめ防止対策推進法」より
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児 童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(イ ンターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が 心身の苦痛を感じているものをいう。
(2)基本認識
① いじめは、人間として決して許されない行為である。
いじめは許されない、いじめる側が悪いという毅然とした態度を徹底する。
いじめは子どもの成長にとって必要であるという考えは認められない。
② いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることである。
全ての子どもを対象とした、いじめに対しての取り組みが重要である。
③ いじめは、大人が気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
④ いじめは、様々な様態がある。
⑤ いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
⑥ いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
⑦ いじめは、解消後も注視が必要である。
⑧ いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを有している。
⑨ いじめは、学校、家庭、社会など全ての関係者が連携して取り組むべき問題である。
3 学校におけるいじめ防止対策等の組織
(1)生徒指導委員会
校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、学級担任等からなるいじめ防止等の対策のための生徒 指導委員会を設置し、必要に応じて委員会を開催する。
(2)職員会議での情報交換・共通理解
月に1度の定例職員会議、朝夕の打ち合わせで、配慮を要する児童や課題について、現状や指 導についての情報交換や共通理解を図る。
4 いじめ未然防止のための取り組み
(1)学級経営の充実
*少人数学級の良さや全校で実施する学期毎のアンケート結果を生かし、担任だけでなく全教 職員で児童の実態を十分に把握し、よりよい学級経営に努める。
*わかる・できる授業の実践に努め、児童一人ひとりが成就感や充実感をもてる授業、ともに 学ぶ楽しさを実感できる授業の実践に努める。
(2)道徳教育の充実
*道徳の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。
*全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心などを育てる。
(3)縦割り班活動の実施
*縦割り班活動のなかで、協力したり協調したりすることを学習し、人とよりよく関わる力を 身に付けさせる。
(4)相談体制の整備
*職員会議の情報交換だけでなく常日頃から学級の問題や課題を相談できる学校体制に努め、 全員が全校児童の担任という意識を持つ。
*アンケート後に学級担任による教育相談を行い、児童一人ひとりの理解に努める。
*スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとも連携していく。
(5)インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策
*全校児童のインターネットに関する使用状況調査を行い、現状把握に努めるとともに、児童 にモラル教育をするなどして迅速に対応する。
(6)学校相互間や地域との連携協力体制の整備
*中学校や保育所と情報交換を行う。
*学童保育での様子や集団登下校での児童の様子について情報を収集する。
5 いじめ早期発見のための取り組み
(1)保護者や地域、関係機関との連携
児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの相談に は、家庭訪問や面談により迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、教育委員会等 の関係諸機関と連携して課題解決に臨む。
(2)学期毎のアンケートの実施
学期毎アンケートを実施し、それをもとに一人ひとりの児童と直接話をして思いをくみ取る。
(3)ノート・日記指導
児童の休み時間や放課後の課外活動の中で児童の様子に目を配ったり、個人ノートや日記など から交友関係や悩みを把握したりする。
6 いじめに対する早期対応
(1)いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。
(2)いじめの事実が確認された場合は、生徒指導委員会を開き、対応を協議する。
(3)いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、 いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(4)いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護 者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。
(5)事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(6)犯罪行為として取り扱うべきいじめについては教育委員会及び警察署等と連携して対処する。
7 重大事態への対処
(1)重大事態の定義(「いじめ防止対策推進法」より)
①いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合
②いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠 席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
③児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合
(2)重大事態への対処
①重大事態が発生した旨を、町教育委員会に速やかに報告する。
②教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機関と の連携を適切にとる。
④上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報 を適切に提